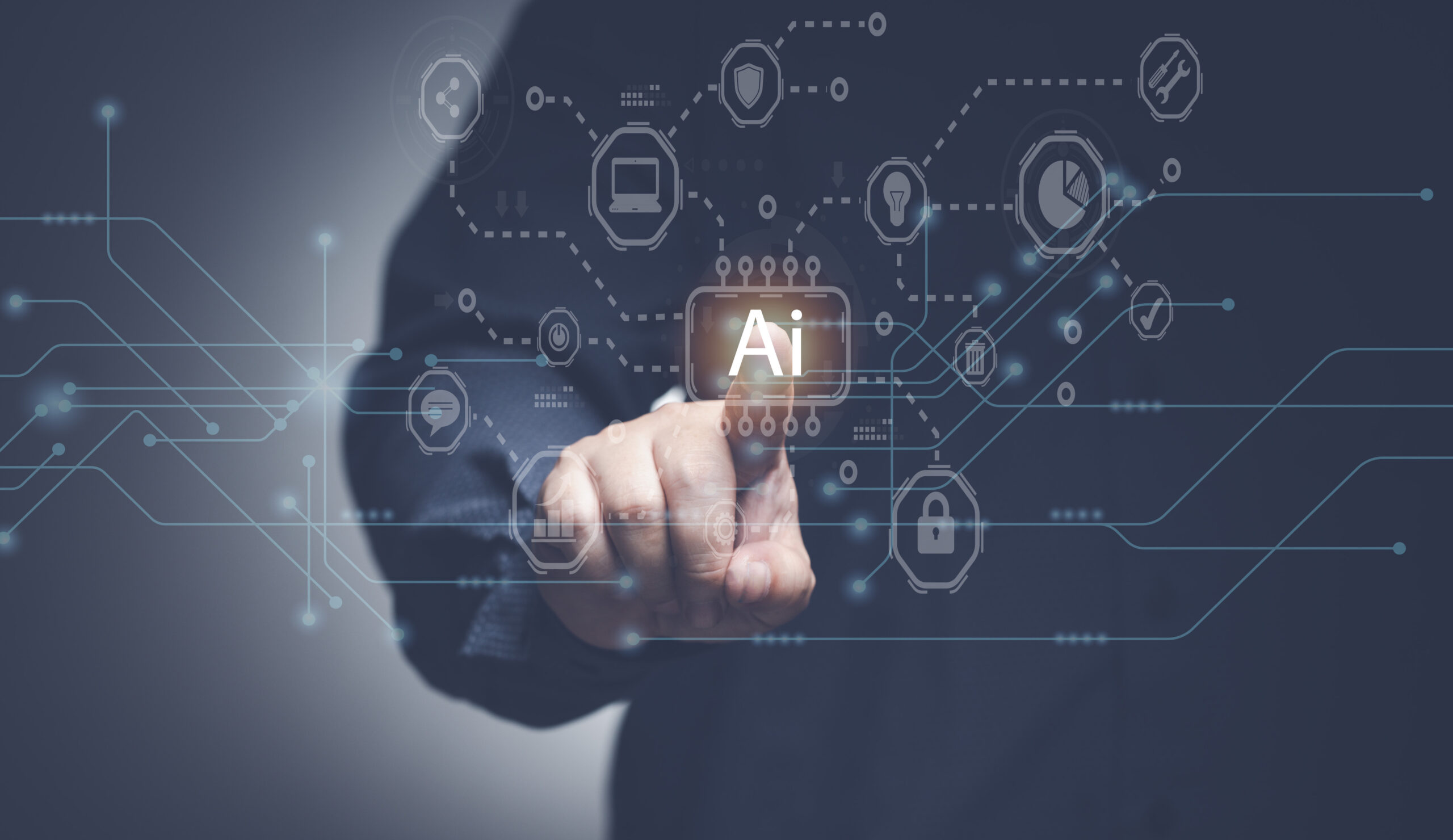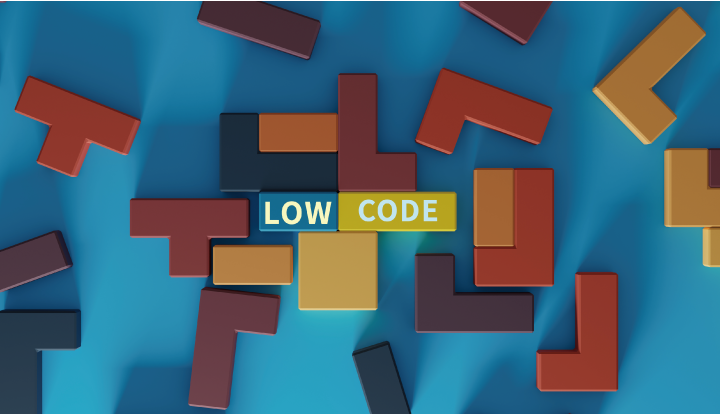Workflow Data Fabricで実現する、AIを活用したワークフローの自動化
日々の業務で、「必要なデータはどこにあるのだろう?」「このデータとあのデータの形式が違うから、手作業で加工しなくては…」 このように「データの壁」に直面し、時間とエネルギーを奪われている人は多いのではないでしょうか。 多くの企業では、部門ごとに独自のシステムやツールが導入された結果、データが孤立し、連携できない「データサイロ化」という問題が慢性化しています。このサイロ化こそが、ビジネスのアイデアやスピードを著しく妨げる最大の要因です。 そこで本記事では、データ活用の非効率を根本から解決し、ビジネスのあり方そのものを変革する新しい考え方「Workflow Data Fabric(ワークフロー・データ・ファブリック)」について、分かりやすく解説します。なぜ、会社のデータは「バラバラ」になってしまうのか?データが自然とバラバラになってしまうその原因は、ビジネスが成長し、各部門が専門的な業務を追求した結果、それぞれに最適なシステムを導入してきた歴史にあります。 人事部には人事システム、営業にはSFA、基幹業務にはERPシステムといった具合に、目的は達成できても、データはそれぞれの「システムという箱」の中に閉じ込められてしまいます。 これが「データサイロ」です。データが孤立すると、部署をまたぐ連携が必要になった際、システムを繋ぐための複雑な開発が必要になったり、あるいは担当者が膨大な手作業でデータを集め、加工し直したりする非効率が発生します。 この手間が、データの活用スピードを鈍らせ、企業の機動力を大きく低下させているのです。従来のデータ管理手法の課題これまで、この「データの壁」を壊すために、企業は様々なデータ管理手法を導入してきました。例えば、データウェアハウス(DWH)やデータレイクといった仕組みです。これらの手法は、「データをすべて一箇所に集める」という発想に基づいており、特定の分析目的には非常に有効でした。 しかし、データの種類が爆発的に増え、ビジネスの変化のスピードが加速する現代においては、その限界が見え始めています。すべてのデータを集めるには、莫大なコストと時間がかかります。 また、データの移動と複製を繰り返すことで、セキュリティリスクが増大し、何より「データの鮮度」が失われてしまいます。 データは生き物です。集めている間に古くなり、必要な情報が手に入ったときには、すでにビジネスのチャンスを逃した後、という事態も少なくありません。データを「必要な時に、必要な形」で届ける仕組み「Workflow Data Fabric」 Workflow Data Fabric(WDF)は、単なる新しい技術というよりも、企業におけるデータ活用のあり方そのものを変える「新しい考え方」です。 WDFが目指すのは、「誰もがデータにアクセスし、活用できる状態」、つまり「データ活用を身近にする」ことです。 これまでのデータ管理が専門家だけのものであったのに対し、WDFは必要なデータを、必要な人がすぐに使える状態にします。 顧客からの問い合わせ、サプライチェーンの変動、社内での承認状況など、ビジネスを取り巻く情報はリアルタイムで変化します。 WDFは、この変化に合わせて、常に最新のデータを提供できるため、瞬時の意思決定と行動を可能にするという価値を持っているのです。データ基盤のパラダイムシフト:集めないデータ管理従来のデータ管理が「データを一箇所に集める」ことに固執していたのに対し、WDFはデータ基盤におけるパラダイムシフト、すなわち「考え方の転換」をもたらします。 WDFの画期的なアプローチは、「データをその場に置いたまま、仮想的に統合する」という点です。 それぞれのシステムにあるデータを無理に移動させることなく、まるで一つにまとまっているかのように扱える仮想的な層を作ります。 これにより、データの移動に伴うコストやリスクを削減しつつ、異なるシステム間の壁を乗り越えてデータを統合的に活用できるようになるのです。「データファブリック」と「Workflow Data Fabric」は、何が違う?「データファブリック」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、データの「統合・接続」に焦点を当てた仕組みです。データを仮想的に繋ぎ、アクセスを容易にする技術基盤を指します。 一方、Workflow Data Fabricは、この基盤に加えて「データ活用のプロセス全体」を自動化・最適化する概念までを含みます。 単にデータを繋ぐだけでなく、データ収集から加工、分析、そしてビジネスアプリケーションへの連携までの一連の「ワークフロー」全体を自動化・効率化する仕組みです。 つまり、WDFは「データを見つける」だけで満足せず、「そのデータを活用して新しい価値を生み出すまでの流れ」を、人の手を介さずに自動で完結させるという、一段上の視点を持つのです。Workflow Data Fabricがもたらす革新的な価値つづいて、Workflow Data Fabricには、どのような価値があるのかご説明します。「データ」がAI活用のための「源」に変わるWorkflow Data Fabricの最大の強みの一つは、データをAIがすぐに活用できる形で提供する仕組みにあります。 AIは、質の高いデータがなければ期待通りに機能しません。WDFは、複数のシステムにまたがるバラバラなデータを統合し、AIがリアルタイムで学習・分析するための基盤を自動で構築します。 これにより、データはAIにとって極めて価値の高い「源」に変わり、AIはより正確で、より速い判断を下せるようになるのです。 これは特に、ServiceNowのようなプラットフォーム上で、異なる業務データを横断的に統合する際に強力な優位性となります。思考から実行までを加速する「アクション」これまでのデータ活用は、分析の結果をレポートとして表示する「見る」こと、つまり「思考」で終わることがほとんどでした。 しかし、WDFは違います。データ分析の結果をトリガーに、「次の行動(アクション)」を自動で起こすことを可能にします。 例えば、システムの監視データから異常値を検知したら、それが単なるアラートで終わるのではなく、WDFを通じて自動で担当者に必要な情報と連携してアラートを飛ばす、といった一連の流れを実現。 また、顧客の問い合わせ内容をAIが分析し、最適な回答を自動で生成・提示するなど、データからAIを介した「アクション」の流れが生まれることで、業務のスピードが劇的に加速します。ワークフローを自動化し、ビジネスを再構築Workflow Data Fabricは、データから導き出されたインサイトを基に、複雑な業務プロセス全体を自動化し、ビジネスを再構築します。 これまでのデータ活用が「分析」で留まっていたのに対し、WDFは分析結果をトリガーにして、部署をまたぐ連携や、手作業で行っていた業務を巻き込み、複雑なワークフロー全体を自動で実行。 これにより、例えば顧客からの要望が、営業、開発、サポートといった複数の部門をシームレスに流れ、解決までが劇的に効率化されるといったメリットが生まれます。ServiceNowが実現する、理想の「Workflow Data Fabric」 Workflow Data Fabricの概念を実現する上で、ServiceNowが特に優位性を持つのは、「統合型」プラットフォームを提供している点です。 従来の企業がバラバラなシステム管理に苦しんでいたのに対し、ServiceNowは単一のプラットフォーム上で、データとワークフローを統合する基盤を提供します。 ServiceNowはこのプラットフォーム上で「Data」「Action」「Workflows」の3つの要素をシームレスに連携させています。 「データ」が単なる情報ではなく、AIを活かす「源」となり、それが次の「アクション」を自動で生み出し、最終的にビジネスの複雑な「ワークフロー」全体を自動化する。 この一連のサイクルが単一の基盤上で実現されるからこそ、企業はビジネス全体のスピードと効率を飛躍的に向上させることができるのです。まとめWorkflow Data Fabricは、現代の企業が直面する「データの壁」を打ち破る、画期的な考え方です。 それは、「データを一箇所に集めるのではなく、必要な時に、必要な人に届ける」という、これまでの常識を覆すアプローチにあります。 WDFによって、データは単なる静的な情報から、AIを動かし、自律的に「アクション」を生み出すビジネスの動力源へと進化します。 この仕組みを実現するには、データ、AI、そしてワークフローという三つの要素をシームレスに繋ぐことができるServiceNowのような統合プラットフォームが有効な選択肢といえるでしょう。 これからのビジネス競争において、Workflow Data Fabricのような仕組みは、企業の機動力と競争力を左右する重要な要素となります。 ぜひこの機会に、未来のデータ活用への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。 ServiceNowを基盤としたWorkflow Data Fabricにご興味があれば、ぜひお気軽に株式会社DTSまでご相談ください。