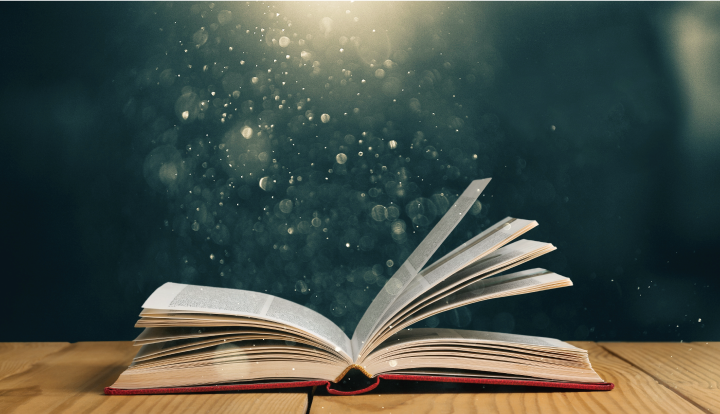カスタマーサポートツールの選び方:ServiceNow「CSM」&その他7選を比較
近年、企業のカスタマーサポートは、顧客の問い合わせチャネルが増えたことにより対応の煩雑さを増しています。たとえば、電話、メール、SNSなど、異なる媒体からの問い合わせを一括管理することは、多くの企業にとって難題になっています。ここではServiceNowのサービスを中心に、カスタマーサポートツールの概要や注意点について解説します。カスタマーサポートツールとは? 種類別に解説 カスタマーサポートツールとは、企業が顧客へのサポートを提供するために使用するソフトウェアやツールの総称です。カスタマーサポートツールには、顧客からの問い合わせや要望に迅速かつ効果的に対応するための機能が揃っています。カスタマーサポートツールを利用することで、顧客との効率的なコミュニケーションや問題解決をサポートし、関係構築や顧客データの蓄積を行うことができます。 続いて、カスタマーサポートツールの種類を紹介します。問い合わせ管理システム問い合わせを一括管理するシステムのことを「問い合わせ管理システム」といいます。電話やメール、SNS、チャットなど複数のチャネルに分散していた問い合わせを、統合的に管理することで、情報の漏れや不手際を防ぐことができます。例えば、メールの対応については「誰がいつ対応したか」「対応中か」「未対応か」といったステータスをリアルタイムで管理できることもメリットです。返信漏れや作業ミスが減るほか、部署を跨いだ情報共有も円滑に行えます。複数のチャネルから顧客対応をしている企業におすすめのシステムといえます。CRM(顧客情報管理)CRM(顧客情報管理)は、企業が顧客との関係を強化し、顧客満足度を向上させるための戦略やツールのことです。CRMは、顧客の基本情報や購買履歴、問い合わせ履歴などのデータを一括管理することで、蓄積したデータを他の予約システムなどと連携することができます。問い合わせ管理システムと連携することもできるため、問い合わせ情報を蓄積し最適な顧客対応の答えを出すことも可能です。顧客データの管理が膨大になり、現状のシステムでは管理しきれない、または共有がスムーズに行えないと感じている企業におすすめです。FAQとチャットボット顧客への回答支援には、顧客が回答を見つけやすくする「FAQ」と「チャットボットでの回答」があります。 FAQは、頻度の高い顧客の質問に対する回答を一問一答でまとめたコンテンツです。Q&Aがシンプルに質問に対する回答のまとめであるのに対し、FAQは、顧客がスムーズに回答にたどり着くために「よくある質問」をまとめたものになります。なかには、自己学習により顧客の質問を先回りして回答するものもあり、Q&Aではたどり着けない回答を見つけることができます。 チャットボットとは、チャットを用いた自動会話プログラムのことを指します。最近企業のHPなどで「ご質問はありますか?」「なにかお困りですか?」とポップアップが立ち上がることがよくありますが、それがチャットボットです。チャットボットを導入することで問い合わせが減るため、クレームやサポートセンターへの問い合わせの多い企業におすすめです。カスタマーサポートツールと連携したチャットツールカスタマーサポートツールに搭載されているチャットツールを利用することで、顧客とカスタマーサポートツールのコミュニケーションの活性化が可能です。例えば、メールや電話、SNSの代わりにカスタマーサポートツールと連携したチャットツールを運用することで、顧客情報を把握しつつ多数の顧客へ同時に情報を送信することも可能になり、円滑なサポートが行えます。また、顧客情報や対応履歴を共有している前提で社内の情報伝達が行えることもメリットです。それゆえ部署間のコミュニケーションの連携が多い企業などで有効です。カスタマーサポートツールの選び方 ここまでの解説で、どのカスタマーサポートツールも魅力的に見えたかもしれません。しかし、自社の目的によって選択するべきカスタマーサポートツールは異なります。 まず重要なのはコストとの兼ね合いです。事業内容によっていらない機能もあるので、適切な機能があり、予算的にも無理のないツールを選びましょう。また、すでに使っているツールやシステムとの互換性も重要です。ツールの導入後に互換性がないことが発覚した場合、ツールの再導入のために余計なコストがかかってしまいます。 一方で、ツールの導入後に新しい機能が必要となった場合、追加機能を備えたツールを導入するか、ツールの入れ替えが求められ、追加でコストがかかることが想定されます。事業拡大やツールの用途の広がりが予測される場合は、多機能ツールを導入することも重要です。カスタマーサポートツール7選ここではServiceNowを中心に、さまざまな特徴を持ったカスタマーサポートツールを7つ紹介します。ServiceNowServiceNowのCSM(カスタマーサービスマネジメント)は、ServiceNow独自のカスタマーサポート向けの製品です。顧客に応じた柔軟なシステム設計が可能で、顧客の課題によって自由に使用する機能をカスタマイズすることができます。2023年7月現在、全世界で800社以上の導入実績があります。Salesforce Sales CloudSalesforce Sales Cloudは、営業支援に特化したカスタマーサポートツールです。リアクションがあった顧客を見込み客として管理することで、営業プロセスの可視化による成約率の向上が期待できます。また、顧客や案件の情報をまとめて管理でき、営業活動だけでなくマーケティング活動にも情報を活用できます。カスタマイズすれば、顧客向けFAQツールとしても活用できます。FastHelp5FastHelp5は、ストレスフリーで使いやすいインターフェイスが特徴のコンタクトセンター向けCRMです。情報の一括管理が容易で、カスタマイズ画面も直観的に操作ができるため運用がしやすく、導入のハードルが低いカスタマーサポートツールといえます。Zoho CRMZoho CRMは、顧客管理と営業支援に特化したカスタマーサポートツールです。世界的に導入実績があり、比較的低価格であることも特徴です。CRM初であるAI音声アシスタントを導入しており、電話やチャットの内容から必要な情報を返答してくれます。ZendeskZendeskは、カスタマーサポート支援型のチャットツールです。顧客が気軽に連絡できるよう、各種SNSと連携が可能で、ベンチャー企業から大企業まで幅広く採用されています。Zendeskには、問い合わせの緊急度を可視化する機能が豊富に備わっており、ユーザーが直感的に問題を把握し、解決することができます。Tayori「誰でもすぐに使い始められる」を売りにしたカスタマーサポートツールです。導入は登録から最短1分で可能です。顧客情報一括管理やFAQの作成に加え、用途に応じたお問い合わせフォームのテンプレート作成が可能です。Freshdesk Support DeskFreshdesk Support Deskは、アメリカ企業で開発された問い合わせ管理に特化したカスタマーサポートツールです。メール、SNS、電話と各種ツールとの相性もよく幅広い情報の一括管理が可能。自動化による業務の効率化が使いやすさをさらに向上させています。例えば、よく送るメールがテンプレートとして記憶するため、ワンクリックで送付することが可能です。まとめいかがでしたでしょうか。企業によって、カスタマーサポートツールの適正は異なります。初期コストや顧客層、組織編成によって最適なツールは変わるでしょう。株式会社 DTS は、ITサービスを通して企業の課題解決や事業促進をサポートする方法を提供しております。カスタマーサポートツールもそのひとつです。DTSは、ITサービスのプロフェッショナルとして、またServiceNowのパートナーとして、これからもお客様のDXをサポートします。