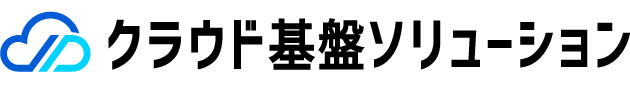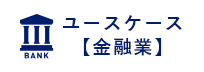DXの推進やサーバー維持管理コスト削減などの観点から、クラウド環境への移行ニーズが高まっています。しかし、オンプレミスからの移行にはいくつかの手順があり、その手順はパブリッククラウドなどの利用経験がない場合は想像しにくいかもしれません。
そこで本記事では、現在最も利用されているクラウドサービスであるAWS(Amazon Web Services)への移行手順をわかりやすく解説します。現行システムをAWSへ移行しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

AWS移行のメリット

まずはAWSに移行するメリットについて解説します。
⦁ 最新のサービスが豊富
⦁ セキュリティ性能が高い
⦁ 開発速度が速くなる
●最新のサービスが豊富
AWSには、業務の効率化などに適した最新のサービスが豊富に揃っています。たとえば、Amazon Bedrockでは話題の生成AIを搭載したアプリケーションの開発が可能。言語モデルのClaude2.1を開発したAnthropicや画像生成AIのStability AI、Metaなどの基盤モデルと連携して開発が行えるため、高いクオリティの生成AIアプリケーションが構築できます。
また、Amazon Bedrockを使って開発されたアプリケーションを利用する際に入力された情報は、基盤モデルの学習に利用されないため、安心して使用可能です。
他にも、組織内のデータと連携しながら対話形式でビジネスやAWS運用に関するアドバイスを提案してくれるAmazon Qなど、新たなサービスも次々にリリースされており、最先端技術を導入できることが大きなメリットとなっています。
●セキュリティ性能が高い
AWSは金融機関や官公庁など、高いセキュリティ性能が求められる業界でも多く導入されています。その背景となっているのは、AWSが世界標準のセキュリティ認証やフレームワークへの準拠を行っていること。たとえば、セキュリティ管理規格のISMS(ISO27001)の取得や、CSAのSTARレベル3相当のツール、FISC安全対策基準への準拠などによって、セキュリティの高さが保証されているのです。
またAWSでは、ユーザーとそれぞれ責任を持つ範囲を責任共有モデルとして明示しています。そのモデルにおいて、AWSはデータセンターなどクラウド環境に関する部分について責任を負っているため、ユーザーはオンプレミスのようにサーバーのセキュリティまで気を回す必要がありません。
●開発速度が速くなる
AWSを活用すれば、ITインフラの追加がわずか数分で行えるため、複雑な構築作業が不要な、スピーディな開発が行えます。
オンプレミスで新しいITインフラを用意する際に時間がかかってしまえば、その分開発も遅れ商機を逃してしまいます。
また、AWSはサーバー台数の増減も柔軟に行えるので、ユーザーのニーズに合わせた調整が可能になり、無駄なコストの削減やユーザビリティの確保も実現。負荷に差がある夜間と日中でのサーバーのスペック変更や、一定値を超える利用量があったときの自動でのサーバーリソース増強などが行えます。
またAWSでは、ユーザーとそれぞれ責任を持つ範囲を責任共有モデルとして明示しています。そのモデルにおいて、AWSはデータセンターなどクラウド環境に関する部分について責任を負っているため、ユーザーはオンプレミスのようにサーバーのセキュリティまで気を回す必要がありません。
●開発速度が速くなる
AWSを活用すれば、ITインフラの追加がわずか数分で行えるため、複雑な構築作業が不要な、スピーディな開発が行えます。
オンプレミスで新しいITインフラを用意する際に時間がかかってしまえば、その分開発も遅れ商機を逃してしまいます。
また、AWSはサーバー台数の増減も柔軟に行えるので、ユーザーのニーズに合わせた調整が可能になり、無駄なコストの削減やユーザビリティの確保も実現。負荷に差がある夜間と日中でのサーバーのスペック変更や、一定値を超える利用量があったときの自動でのサーバーリソース増強などが行えます。
AWS移行の手順

次に、オンプレミスからAWSへ移行するための手順を具体的に解説します。
移行手順には、大きく次の6ステップがあります。
⦁ 移行の目的設定
⦁ 現状の評価・情報資産の棚卸し
⦁ 移行計画の策定
⦁ 現行機器の調査と技術要件の確認
⦁ リハーサルと関係各所への調整
⦁ 移行後のテストと旧システムの廃棄を検討
それぞれ順番に見ていきましょう。
●移行の目的設定
最初に、AWSへ移行する目的や時期、移行対象などを考え、ビジネス目標を設定します。
AWSへ移行することによって何を達成したいのか、と考えるとよいでしょう。AWSにはさまざまな機能があるため、達成したい目標によって利用する機能やアプローチも変わってきます。ここで定める目標に沿って今後のステップが進んでいくため、よく検討してみてください。
●現状の評価・情報資産の棚卸し
次に、現状の評価を行うために、情報資産の棚卸しを行います。移行対象となるシステムのハードウェア資産、ソフトウェア資産、ドキュメント、ログイン情報などを把握し、大まかな移行コストや作業工数を見積ります。
システムやアプリケーションを移行するにあたって技術的な要件がある場合、この時点で洗い出しておくことで以後の行程がスムーズに進行します。このとき、レンタルサーバーなど外部サービスを利用している場合は、解約時期や条件を確認し、追加で必要となるコストや、AWSへの移行で削減できるコストを計算しましょう。
●移行計画の策定
目的設定と情報資産の棚卸しが完了したら、具体的な移行計画の策定に入ります。
AWSに移行するデータやシステムの優先順位の決定、システム停止期間の検討なども、この段階で行います。優先順位については、移行後の影響度合いが小さいものから順次移行するのがセオリーです。
●現行機器の調査と技術要件の確認
移行計画を実行する前に、現行機器の調査と前段階で洗い出した技術的要件の確認を行います。
現在利用しているネットワーク機器やサーバーの性能や容量、稼働状況を把握して、AWS移行後の利用計画策定に反映させます。また、この段階でデータに記録されている機器の情報と実機の状況やスペックが異なる場合は修正を加えましょう。
そして、最初に洗い出した技術的要件についても、問題なく移行できるように対策を講じます。
●リハーサルと関係各所への調整
次にAWSへの移行リハーサルと、システムに関わる社内外の担当者との調整を行います。
このステップにおいて、実際に移行をしてから問題が生じたときに連絡できるよう、外部委託先やAPIの提供先などがあれば把握しておくことをおすすめします。リハーサルでは、移行手順に抜けがないか、想定外の事態が起きることはないかといった観点で確認を行います。
●移行後のテストと旧システムの廃棄を検討
最後のステップとして、移行を実施した後にシステムのテスト運用を行います。
動作時に不具合が生じていないかどうかを移行してからすぐに確認し、その後は継続的に運用コストの適性化を図るようにしましょう。また、旧システム環境については、不要であれば廃棄を検討します。
ただし、移行して間もないタイミングにおいてはトラブルが発生する可能性もあるため、AWSでの運用が軌道に乗ってから行うのがおすすめです。
システムやアプリケーションを移行するにあたって技術的な要件がある場合、この時点で洗い出しておくことで以後の行程がスムーズに進行します。このとき、レンタルサーバーなど外部サービスを利用している場合は、解約時期や条件を確認し、追加で必要となるコストや、AWSへの移行で削減できるコストを計算しましょう。
●移行計画の策定
目的設定と情報資産の棚卸しが完了したら、具体的な移行計画の策定に入ります。
AWSに移行するデータやシステムの優先順位の決定、システム停止期間の検討なども、この段階で行います。優先順位については、移行後の影響度合いが小さいものから順次移行するのがセオリーです。
●現行機器の調査と技術要件の確認
移行計画を実行する前に、現行機器の調査と前段階で洗い出した技術的要件の確認を行います。
現在利用しているネットワーク機器やサーバーの性能や容量、稼働状況を把握して、AWS移行後の利用計画策定に反映させます。また、この段階でデータに記録されている機器の情報と実機の状況やスペックが異なる場合は修正を加えましょう。
そして、最初に洗い出した技術的要件についても、問題なく移行できるように対策を講じます。
●リハーサルと関係各所への調整
次にAWSへの移行リハーサルと、システムに関わる社内外の担当者との調整を行います。
このステップにおいて、実際に移行をしてから問題が生じたときに連絡できるよう、外部委託先やAPIの提供先などがあれば把握しておくことをおすすめします。リハーサルでは、移行手順に抜けがないか、想定外の事態が起きることはないかといった観点で確認を行います。
●移行後のテストと旧システムの廃棄を検討
最後のステップとして、移行を実施した後にシステムのテスト運用を行います。
動作時に不具合が生じていないかどうかを移行してからすぐに確認し、その後は継続的に運用コストの適性化を図るようにしましょう。また、旧システム環境については、不要であれば廃棄を検討します。
ただし、移行して間もないタイミングにおいてはトラブルが発生する可能性もあるため、AWSでの運用が軌道に乗ってから行うのがおすすめです。
現在利用しているネットワーク機器やサーバーの性能や容量、稼働状況を把握して、AWS移行後の利用計画策定に反映させます。また、この段階でデータに記録されている機器の情報と実機の状況やスペックが異なる場合は修正を加えましょう。
そして、最初に洗い出した技術的要件についても、問題なく移行できるように対策を講じます。
●リハーサルと関係各所への調整
次にAWSへの移行リハーサルと、システムに関わる社内外の担当者との調整を行います。
このステップにおいて、実際に移行をしてから問題が生じたときに連絡できるよう、外部委託先やAPIの提供先などがあれば把握しておくことをおすすめします。リハーサルでは、移行手順に抜けがないか、想定外の事態が起きることはないかといった観点で確認を行います。
●移行後のテストと旧システムの廃棄を検討
最後のステップとして、移行を実施した後にシステムのテスト運用を行います。
動作時に不具合が生じていないかどうかを移行してからすぐに確認し、その後は継続的に運用コストの適性化を図るようにしましょう。また、旧システム環境については、不要であれば廃棄を検討します。
ただし、移行して間もないタイミングにおいてはトラブルが発生する可能性もあるため、AWSでの運用が軌道に乗ってから行うのがおすすめです。
動作時に不具合が生じていないかどうかを移行してからすぐに確認し、その後は継続的に運用コストの適性化を図るようにしましょう。また、旧システム環境については、不要であれば廃棄を検討します。
ただし、移行して間もないタイミングにおいてはトラブルが発生する可能性もあるため、AWSでの運用が軌道に乗ってから行うのがおすすめです。
AWS移行時の注意点

最後にAWSへ移行する際の注意点について解説します。
AWSへの移行は、大きなメリットを得ることができる一方で、気をつけておかなければならない点もありますので、本章で紹介することを参考にして移行を検討してみてください。
●オンプレミスと動作環境の違い
移行するシステムの仕様によっては、クラウド環境下で正常に動作しないものや、データ連携がうまくいかなくなるものもあります。たとえば、古いバージョンのOSやミドルウェア上で使用していたシステムなどは、常に最新のライセンスが提供されるAWSに移行する前に、新しいOS上で動作するか確認や修正を行う必要があります。
このように、移行対象となるシステムがAWSへ移行可能な状態か、計画策定時によく検討するようにしましょう。
●コスト管理が必要
AWSは、使用量に応じて料金が発生する従量課金制を採用しています。月額固定制のように料金が一定ではないため、毎月の予算額や使用量を管理しておかないと予想以上に請求額が高くなってしまいます。
使用量の管理には、定期的な請求ダッシュボードの確認や、請求アラーム機能の利用がおすすめです。請求ダッシュボードを確認し、本当に必要なサービスを適正に使用しているかのチェックや、予算額を超えたら通知が来るように請求アラーム機能を設定しておくことで、想定外のコスト負担を防げるでしょう。
使用量の管理には、定期的な請求ダッシュボードの確認や、請求アラーム機能の利用がおすすめです。請求ダッシュボードを確認し、本当に必要なサービスを適正に使用しているかのチェックや、予算額を超えたら通知が来るように請求アラーム機能を設定しておくことで、想定外のコスト負担を防げるでしょう。
まとめ

今回はAWSの移行手順、そして得られるメリットについて解説しました。
AWSでは生成AIなど最新のサービスが利用でき、商機を逃さない柔軟な開発が可能です。AWSへの移行手順は、いくつかの段階を経る必要がありますが、移行後には便利なクラウド環境を導入できます。
移行計画をどのように立てたらよいか悩まれている場合や、AWSのサービスを効率的に利用したい場合は、DTSの「AWS移行支援サービス」をご検討ください。AWSの導入を計画段階からトータルで支援いたします。ご相談はお問い合わせフォームからご連絡ください。
関連してよく読まれているページ
資料ダウンロード
関連サービス
-

AWS 運用保守サービス
豊富な実績、経験を基に、お客様システムを安心・安全にサポートAWSの運用保守は丸ごとDTSにお任せください -

AWS セキュリティマネージドサービス
AWSベストプラクティスをベースとしたAWSで必要となるセキュリティ対策を提供
資料ダウンロードランキング
-
 Microsoft&Azureのサービスについて知りたい方へ
Microsoft&Azureのサービスについて知りたい方へ資料ダウンロード
-
 AWSのクラウドサービスってどのようなサービスがあるの?という方へ
AWSのクラウドサービスってどのようなサービスがあるの?という方へ資料ダウンロード
-
 AWSを検討している情シス担当者の方、必見!
AWSを検討している情シス担当者の方、必見!資料ダウンロード
-
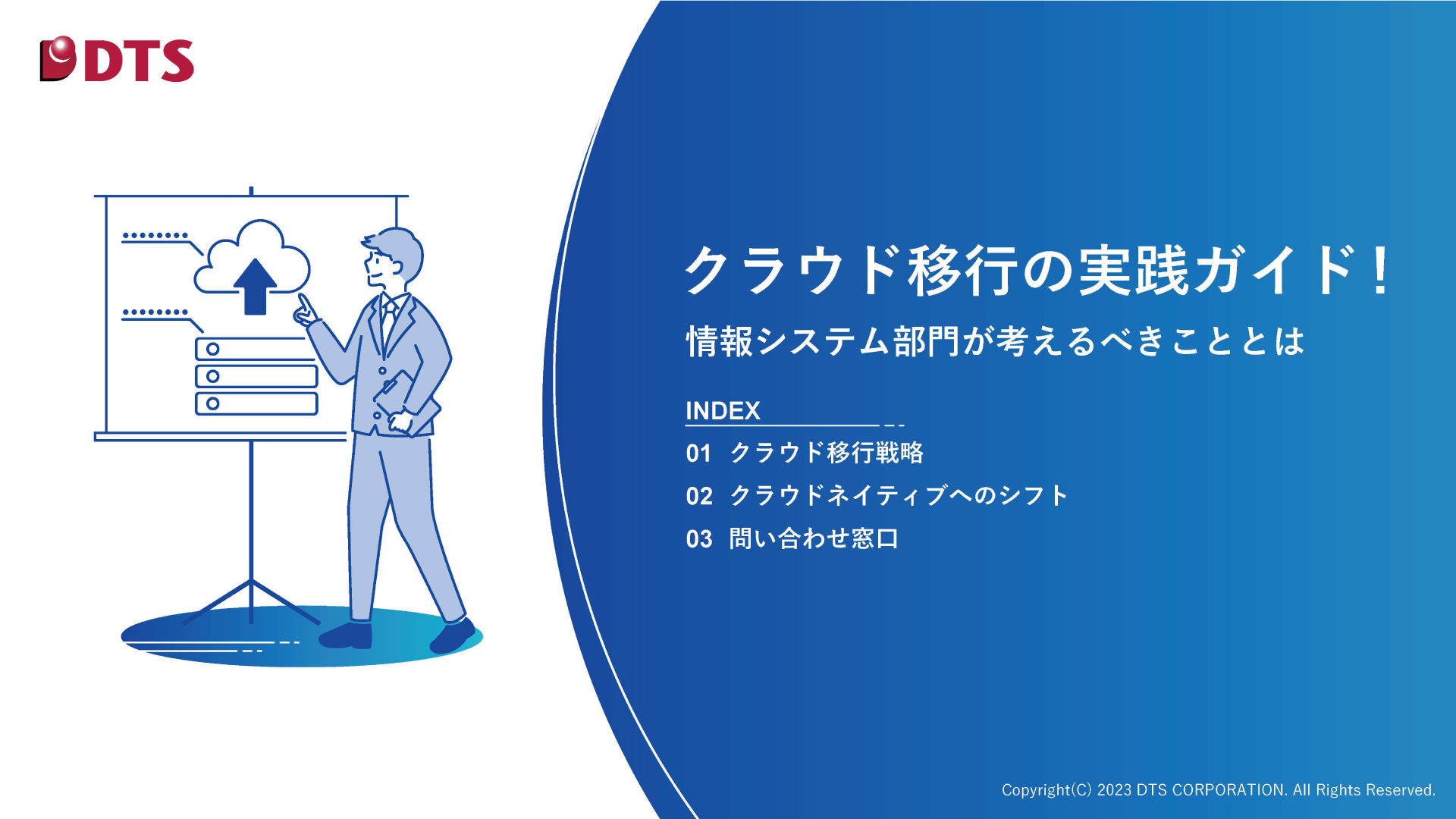 クラウド移行に課題を感じているお客様に!
クラウド移行に課題を感じているお客様に!資料ダウンロード
-
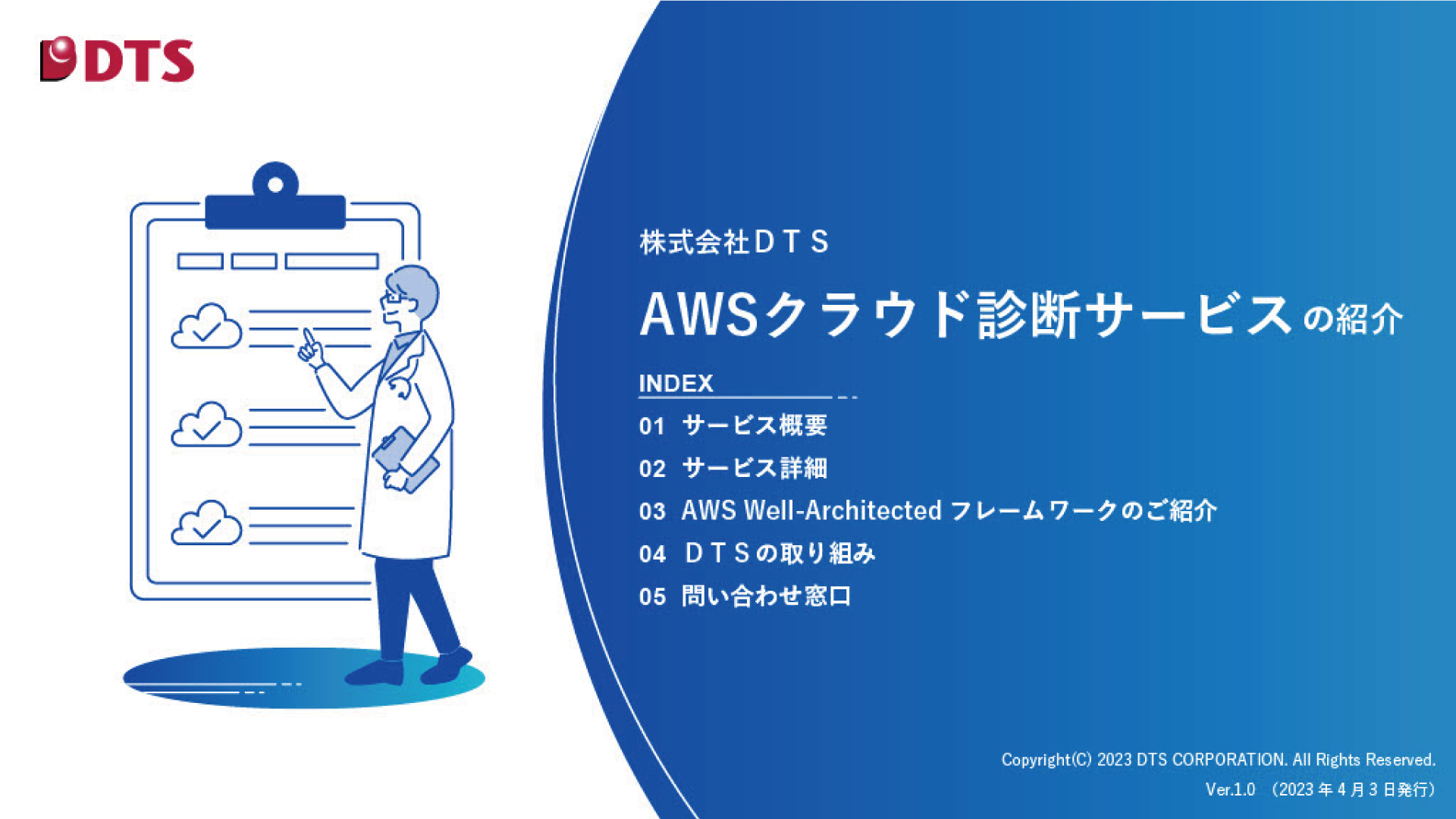 クラウドサービス(AWS)を安全・効果的に使えているか
クラウドサービス(AWS)を安全・効果的に使えているか
診断したいというお客様へ!資料ダウンロード
-
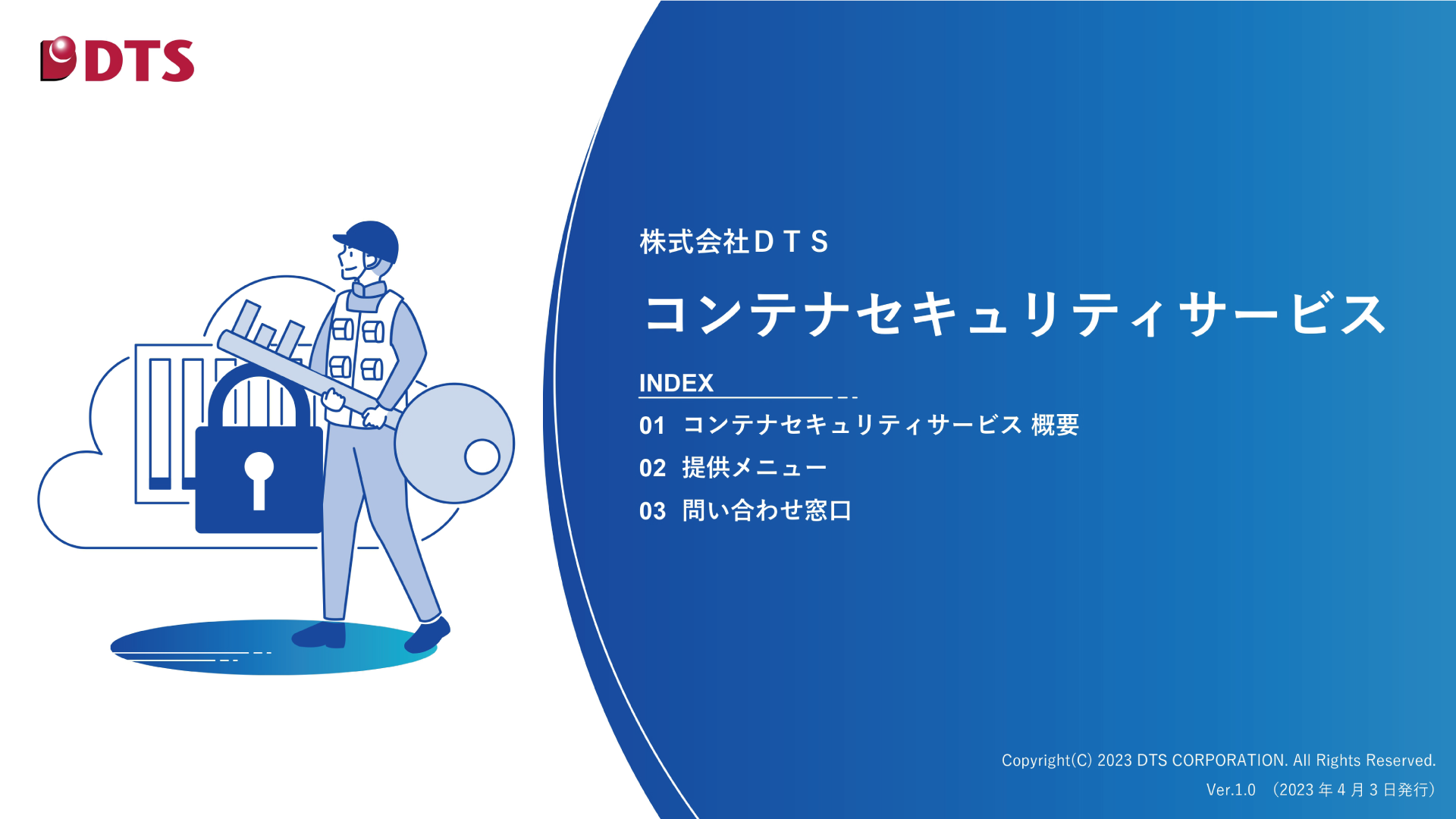 コンテナ利用によるセキュリティリスクに
コンテナ利用によるセキュリティリスクに
不安があるというお客様に!資料ダウンロード
-
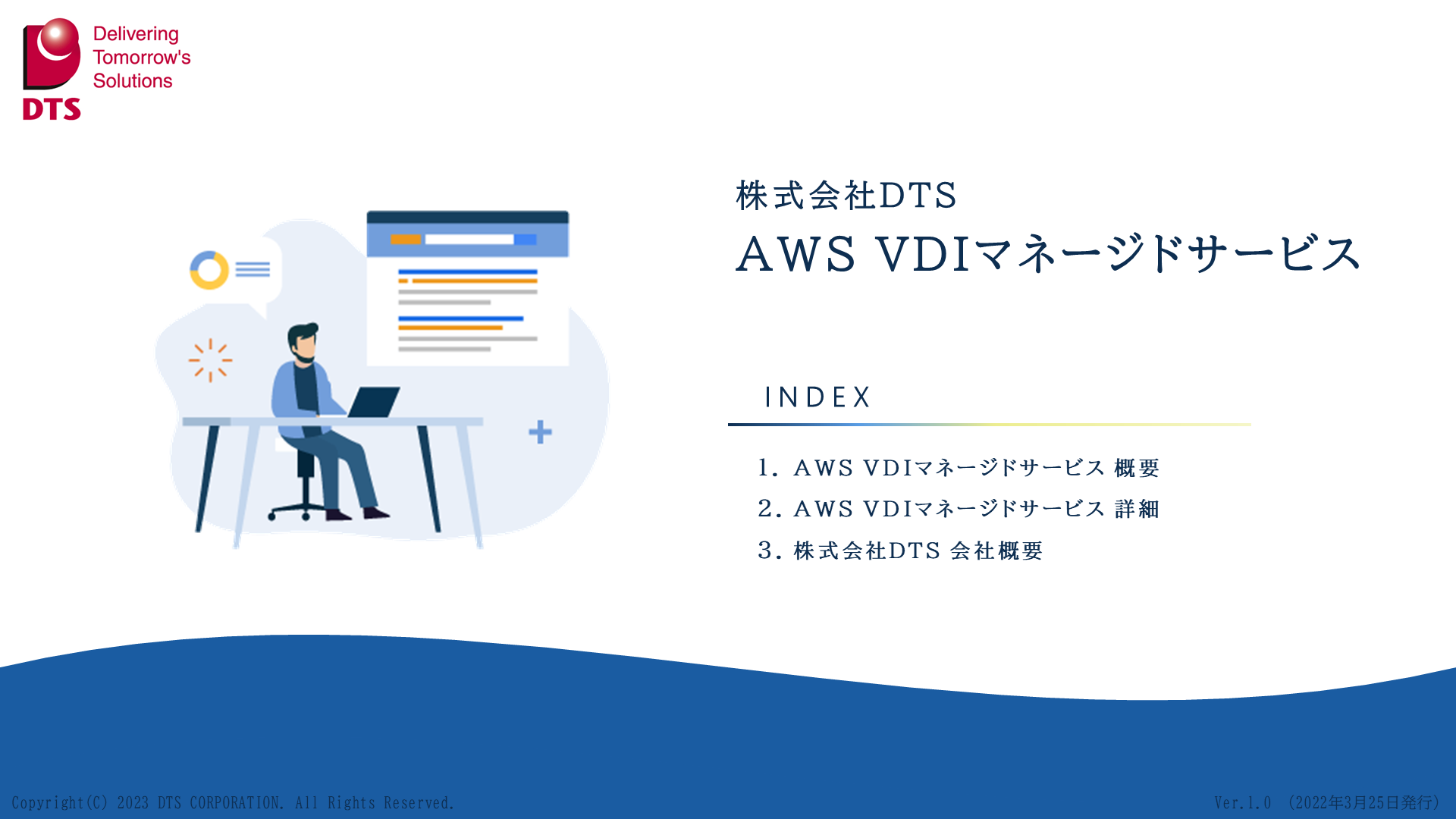 安心のテレワーク環境をすばやく整備!
安心のテレワーク環境をすばやく整備!資料ダウンロード
-
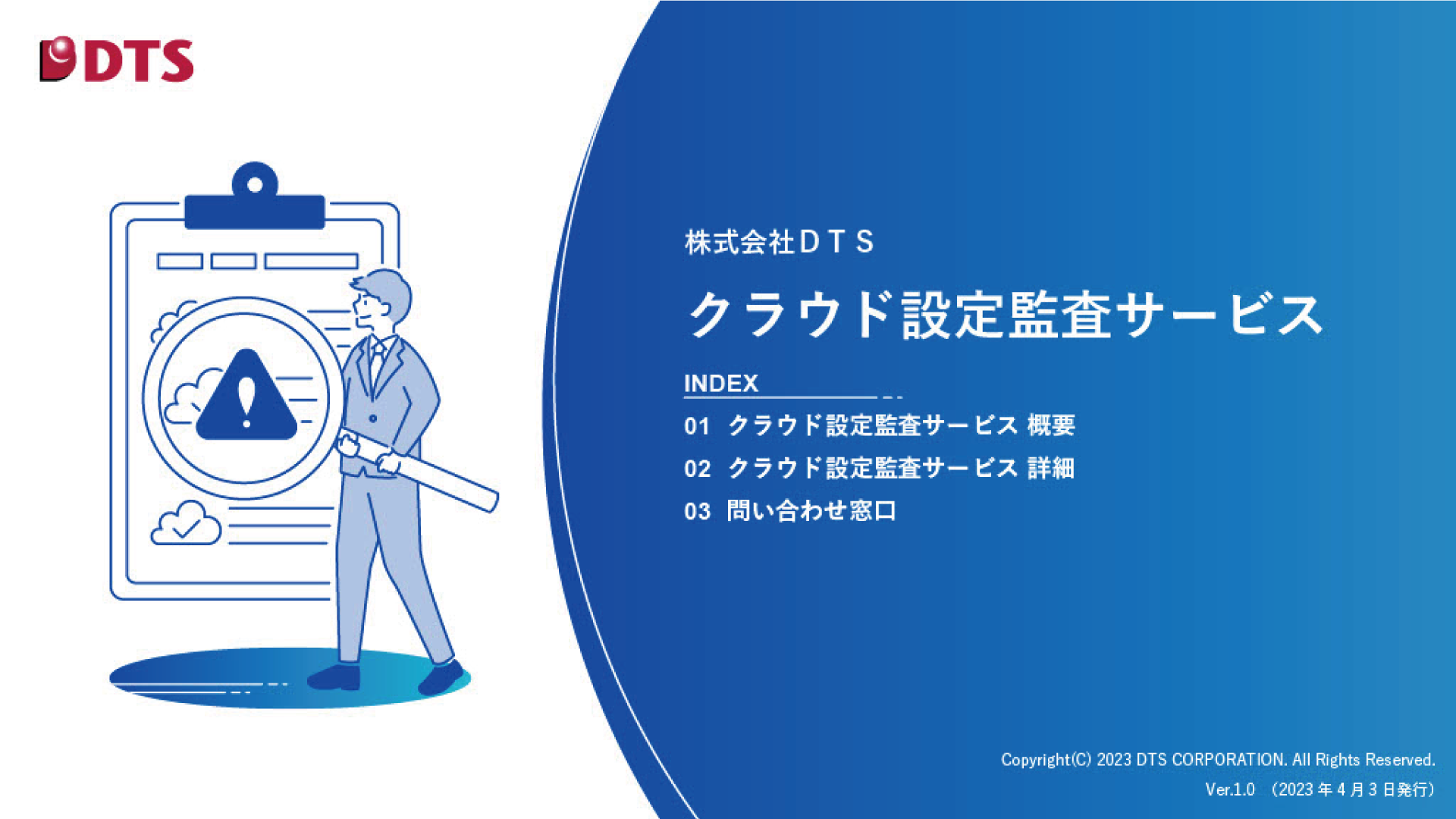 クラウドサービスの利用拡大によるセキュリティリスクの増加に
クラウドサービスの利用拡大によるセキュリティリスクの増加に
不安があるというお客様に!資料ダウンロード
-
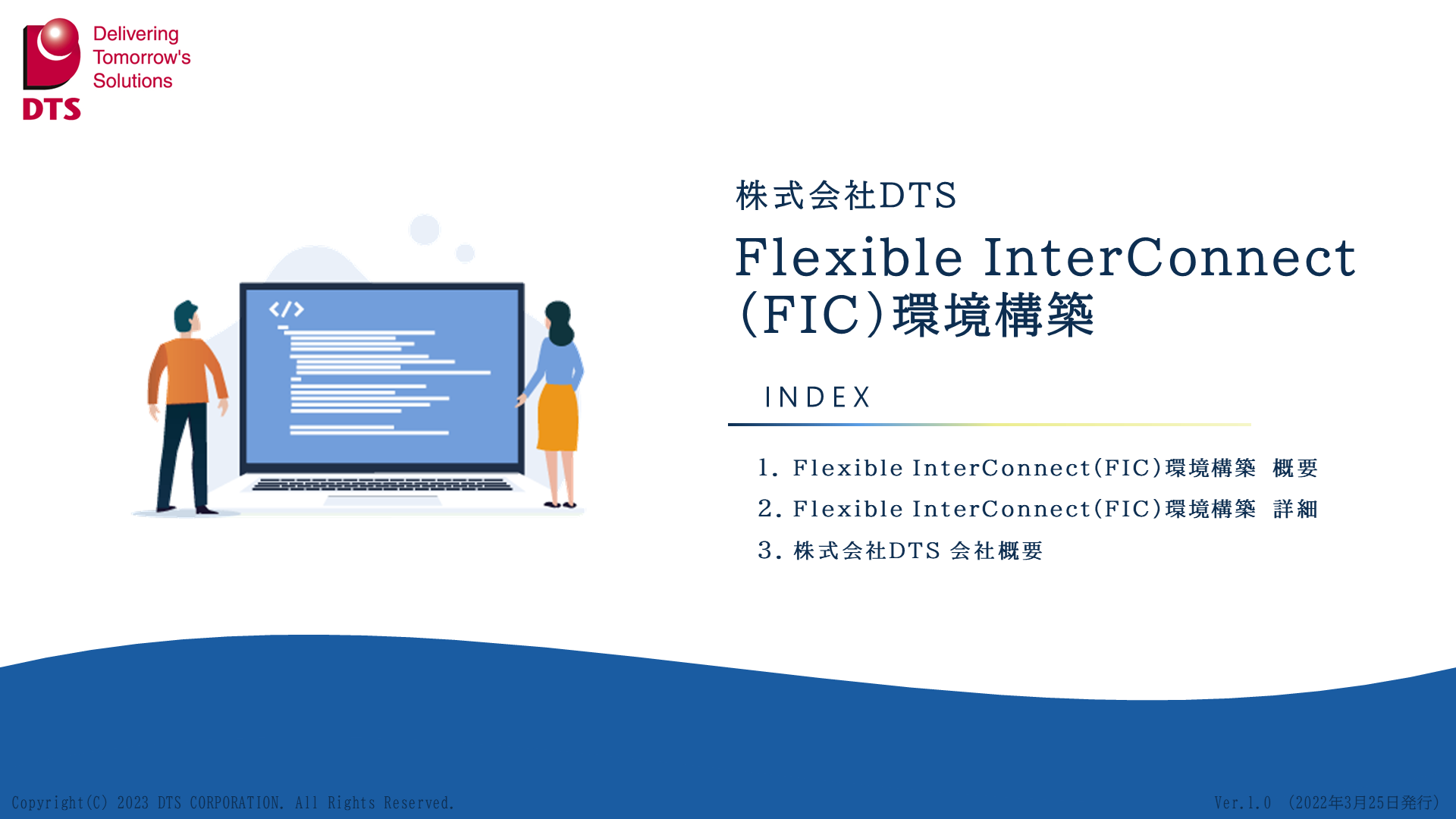 クラウドサービスにセキュアで接続したいお客様へ!
クラウドサービスにセキュアで接続したいお客様へ!資料ダウンロード