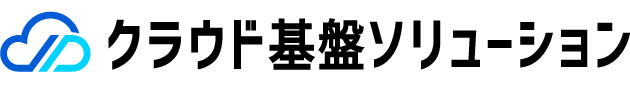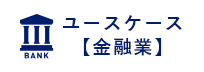IT技術の革新や顧客からの要望の多様化、複雑化などを受け、企業などが運用する大型のシステムにおいては特に、現状の運用環境や利用状況などを把握し、必要に応じて再構築や運用の改善が必要となります。この再構築や改善に繋げる現況調査・診断のことを「システムアセスメント」と呼びます。ここでは「システムアセスメント」の意味と重要性についてご紹介します。

システムアセスメントとは
システムアセスメントとは、主に企業や団体など一定の規模をもつシステムの全体的な性能や各機能、その運用状況や利用環境を客観的に検証および評価することを言います。システムを検証、評価する目的は将来のニーズに対応できるかどうかを判断することや、問題点を洗い出し、万が一のリスクを回避することなどが挙げられます。
システム運用管理が抱える課題

担当となるITインフラ部門は、システムを安定的に稼働させる役割を担い、日々、各種システム内の監視やハードウェアやソフトウェアの追加、更新などの業務で忙殺されています。そのため、インフラ整備や運用改善などシステムアセスメントの重要性は認めつつも、下記のような課題から手が回らないのが実情ではないでしょうか。
●運用担当者の慢性的な人員不足
独立行政法人情報処理推進機構が調査した「IT人材白書2020」の中で、IT 人材の量に対する不足感という設問に対して「大幅に不足している」という回答が、300名以下の企業で2018年度が25.4%、2019年度では29.7%に上るなど、ITインフラを担当する人材の少なさは年々、増加傾向にあります。
一方で、企業ネットワーク内で稼働するシステムは、多くの要素で構成されているため、ITインフラ部門の業務は多岐にわたります。これらの業務を1人ないし、少人数で担当しているため、各人の業務範囲が広く、属人性も高くなっています。
このような状況下で担当者の不在時にトラブルが発生すれば、業務に深刻な影響を及ぼします。そのため人材確保は喫緊の課題と言えます。
●日々、進化する技術の習得が追いつかない
ITインフラの担当者はITの基本的な知識、技術は当然として、進化する新しい技術の学習、これらの技術により生まれた機器などの情報のキャッチアップなど、日々の業務のほかに幅広い知識やスキルの習得が求められます。
さらに、ITインフラの担当者にとって、管理するシステムは年々、規模が拡大し、仮想環境やマルチクラウドなどが混在することで複雑さも増しています。一方で、事業部門においては高いサービス品質や運用品質を求められるため、インプットしなくてはならない量が多い割に、それに割ける時間がなく、ITインフラの部門では常に、技術、スキル不足が問題となっています。
●システム運用の自動化の範囲
技術の発展が目覚ましいIT業界だからこそ、システムの運用を自動化で賄う傾向が強く、それに関連したサービスやプロダクトなども数多く世の中に出ています。システム運用を自動化すれば、人為的なミスがなくなり、人員不足の問題も解決できる期待が持てますが、現実は、どの業務、どの工程までを自動化できるのか、その範囲決めは悩ましい問題の一つです。
既存ノウハウや自動化できる業務の洗い出しなど、自動化の範囲決めにはさまざまな要件をまとめる必要があります。しかし、その工数さえ、先に挙げた通り、ITインフラ部門では捻出するのが難しく、結局、自動化の検討は後回しになり、さらに、現状は問題ないから、と先送りにされるというケースは少なくありません。
●システムの一元管理の煩雑さ
今や社内システムが単一である企業はそう多くないでしょう。ほとんどは、ベンダーなどの異なる複数のハードウェアやソフトウェアで構成されており、さらにその環境も物によってオンプレミスやクラウドなどに分けられ、システムは複雑化、多様化が進んでいます。
これらを別個に管理することはそもそもが非効率であり、さらに運用や管理だけでなく、システムの構成情報やサービスや機器の購入日、サポート期間などの情報の管理も必要です。
こういった管理そのものが煩雑であることに加え、Excelなどでの杜撰な管理法や、前任者からの引き継ぎが十分でないことから、「いつ更新されたかわかっていない」と一元管理からはほど遠い管理体制になっていることもよくある話です。
システムアセスメントの基本手順
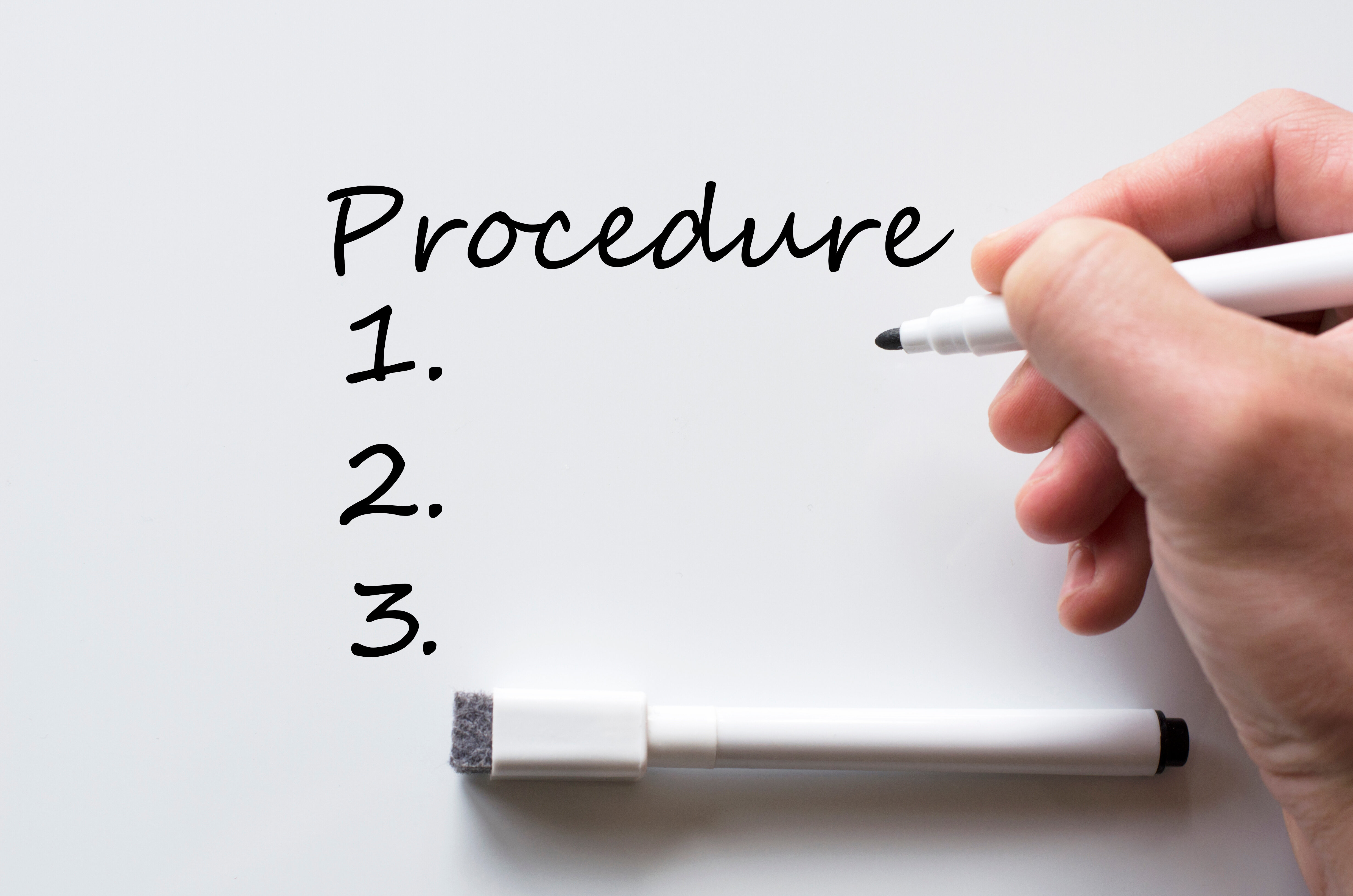
具体的にシステムアセスメントを実施するには何をしていけば良いのか。基本的な手順は下記の通りです。
(1)目的の明確化
(2)調査対象の範囲の決定
(3)調査計画の策定
(4)調査実施
(5)調査結果の分析
(6)調査報告書の作成
まずは自社のシステムを見える化した上で、現在の課題や問題点を洗い出し、何を解決、最適化するのか実施するシステムアセスメントの目的を明確化します。 (2)調査対象の範囲の決定
担当者からのヒアリング、現存する資料の査読などを経て、調査対象の範囲を決定します。 (3)調査計画の策定
各施策の実施のタイミング、場合によってシステムの一時停止期間など、報告書の提出までのスケジュール、さらにそれにかかる予算や工数などを査定します。 (4)調査実施
対象となるシステムの運用環境や利用状況、具体的にはシステムの構成や設計、運用状況、セキュリティ面、機器の性能や保守体制、運用管理、利用者の利用状況などが調査対象となります。 (5)調査結果の分析
現状分析のほか、将来想定されるリスクに備えるための一連の活動(リスクの特定・分析・評価など)も対象となります。 (6)調査報告書の作成
現状報告、既存システムが抱える将来的なリスクのほか、改善提案やシステム全体の最適化計画まで含めた調査報告書を作成します。
●システム課題の洗い出し・分析・評価
システムアセスメントを実施する際に最も難しいのが既存システムの課題の洗い出しです。これを解決する一つの方法としてポピュラーなものが「As-Is/To-be」です。現状のボトルネックとなっている要件を見つけ出すのに最適な「As-Is/To-be」について少し触れたいと思います。
・As-Is/To-be分析とは
現状を指す「As is」と理想の状態を指す「To be」の間にある差分を課題として捉え、「To be」にするには具体的にどういった行動を起こすべきかを明確にし、目標達成までの道筋を探るのが「As-is/To-be」分析です。
仮にコールセンターの受電・顧客管理システムを「As-is/To-be」分析する具体的な手順は下記の通りです。
(1)To-beを設定する未来における理想を設定します。
<理想>
・システムアップデートを営業時間後に実施する
・受電後のトーク履歴の入力が5分/件にする(総受電数を増やす) (2)As-isを設定する
To-beに呼応する形で課題を考えます。
<現状>
・システムアップデートが営業時間中に行われる
・受電後のトーク履歴の入力が10分/件かかる (3)課題を抽出する
<課題>
差分は何を解消すれば理想の状態になるのかを考えます。
・システムアップデートを社員が実行しているためどうしても
平日の営業時間に実行される
→人力ではなく自動化で解消
・入力項目が多い上、煩雑
→入力項目の一部を手書き入力にする (4)課題に優先順位をつける
システムの自動化には時間がかかるが、UI/UXの変更は比較的簡単なのでこちらを優先する。 (5)課題を行動に落とし込む
上記を実行します。これに加え、実行したアクションは必ず振り返りを実行しましょう。
・As-Is/To-be分析の活用方法
「As-is/To-be」分析で課題が抽出された後、どのように実行していけば良いのか。もう少し掘り下げてみたいと思います。
■課題を抽出する「As is」と「To be」のギャップを見つけたら、そのギャップをどのように埋めていくかを考えるのがこの工程ですが、便利なのが、トヨタ生産方式における分析方法として知られている6W2Hというフレームワークです。端的にいえば、下記の8つの視点で課題を突き詰めることで必要なアクションを浮き彫りにするという方法です。
| When(いつ) | いつ提供するのか?(例:2025年9月中旬にウェビナー開催) |
| Where(どこで) | どこで提供するのか?(例:オンライン、国内市場向け) |
| Who(誰が) | 誰が提供するのか?(例:マーケティング部と営業部が共同で実施) |
| Whom(誰に) | 誰に提供するのか?(例:エンタープライズ企業の情報システム部門) |
| What(何を) | 何を提供するのか?(例:DX推進に役立つ事例とソリューション) |
| Why(なぜ) | なぜ提供するのか?(例:新規リード獲得と信頼構築のため) |
| How(どのように) | どのように提供するのか?(例:Zoomを使ったウェビナー形式) |
| How much(いくら) | いくらで提供するのか?(例:無料参加、社内コストは〇万円) |
6W2Hで課題を抽出したら、一度に全てを実行するのではなく、優先順位をつけましょう。優先順位の付け方はケースバイケースとなりますが、例えば、コストや時間をかけずにすぐに実行できるものから、あるいは全体の目標を達成するのに最も重要な項目からなど、が挙げられます。
■課題を行動に落とし込む課題を実行する優先順位を決めたら、実際に行動に落とし込みますが、この際、行動する内容と、行動したことで何を持って成果(達成)とするかを明確にしましょう。さらに、実行範囲と期間、場合によっては中止するケースまで想定しておけば、より行動が具体的となり、行動の妥当性が図れます。
まとめ
社内システムの評価、検証の必要性は理解できていても、コスト面や工数などからなかなか実施できていない企業も多いと思います。一方でシステムは日々、規模が拡張され、システムアセスメントの重要性は増すばかり。こんなジレンマに陥っている方はぜひ、1,400社を超えるシステム開発の実績があり、経験豊富なエンジニアが、伴走型トータルサポートするDTSへご相談ください。
関連してよく読まれているページ
資料ダウンロード
関連サービス
-

AWS 運用保守サービス
豊富な実績、経験を基に、お客様システムを安心・安全にサポートAWSの運用保守は丸ごとDTSにお任せください -

AWS セキュリティマネージドサービス
AWSベストプラクティスをベースとしたAWSで必要となるセキュリティ対策を提供
資料ダウンロードランキング
-
 Microsoft&Azureのサービスについて知りたい方へ
Microsoft&Azureのサービスについて知りたい方へ資料ダウンロード
-
 AWSのクラウドサービスってどのようなサービスがあるの?という方へ
AWSのクラウドサービスってどのようなサービスがあるの?という方へ資料ダウンロード
-
 AWSを検討している情シス担当者の方、必見!
AWSを検討している情シス担当者の方、必見!資料ダウンロード
-
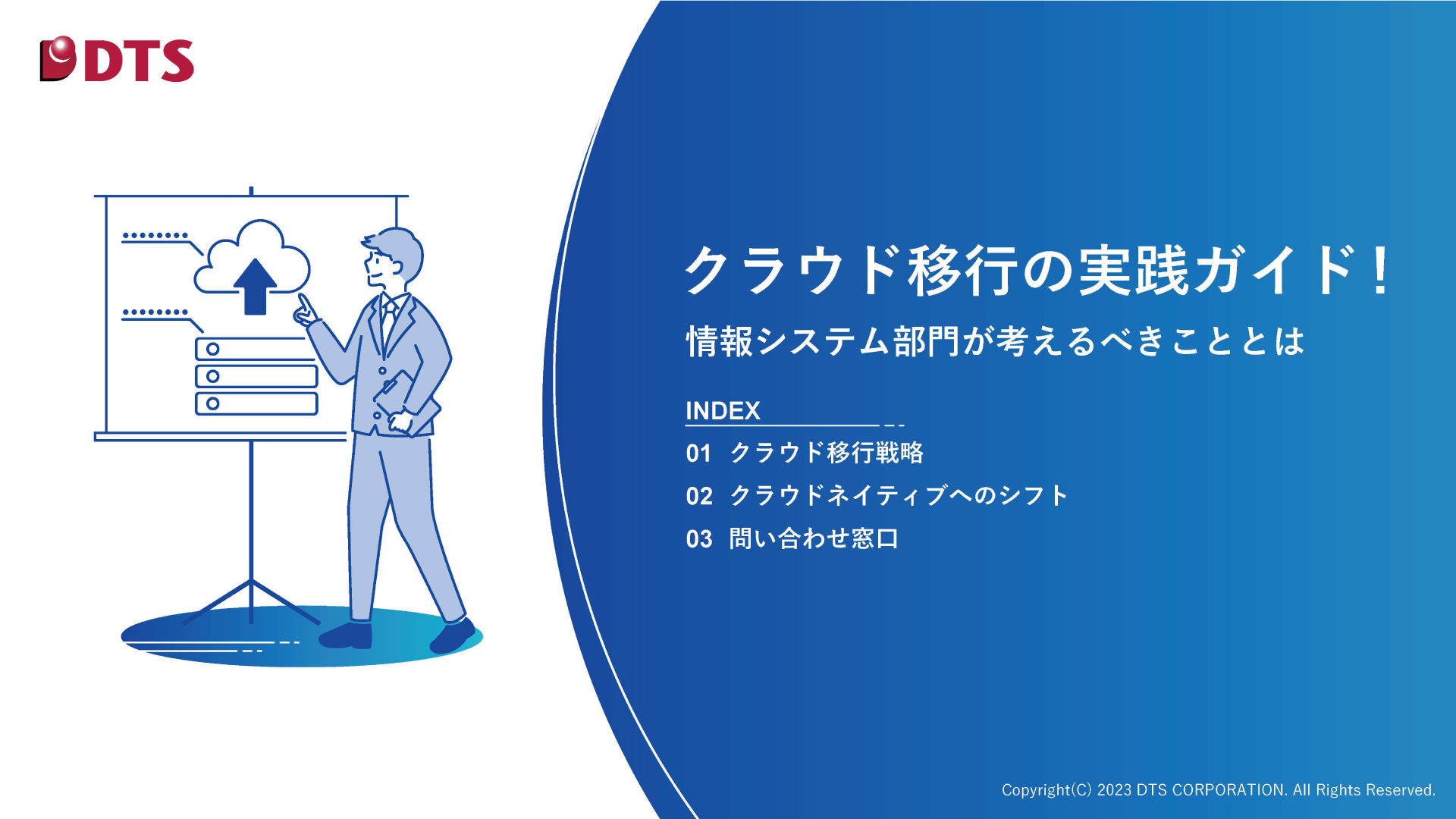 クラウド移行に課題を感じているお客様に!
クラウド移行に課題を感じているお客様に!資料ダウンロード
-
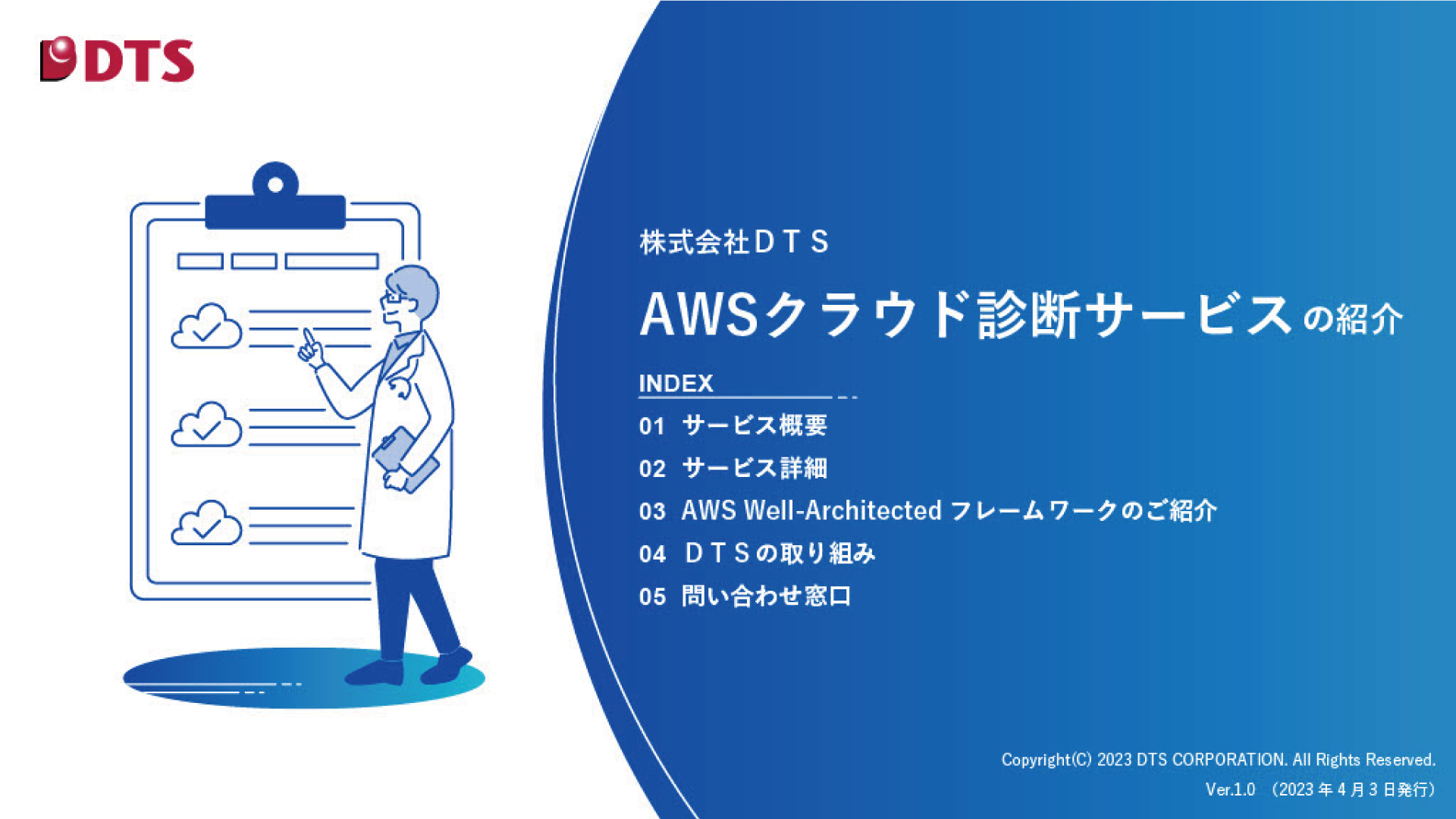 クラウドサービス(AWS)を安全・効果的に使えているか
クラウドサービス(AWS)を安全・効果的に使えているか
診断したいというお客様へ!資料ダウンロード
-
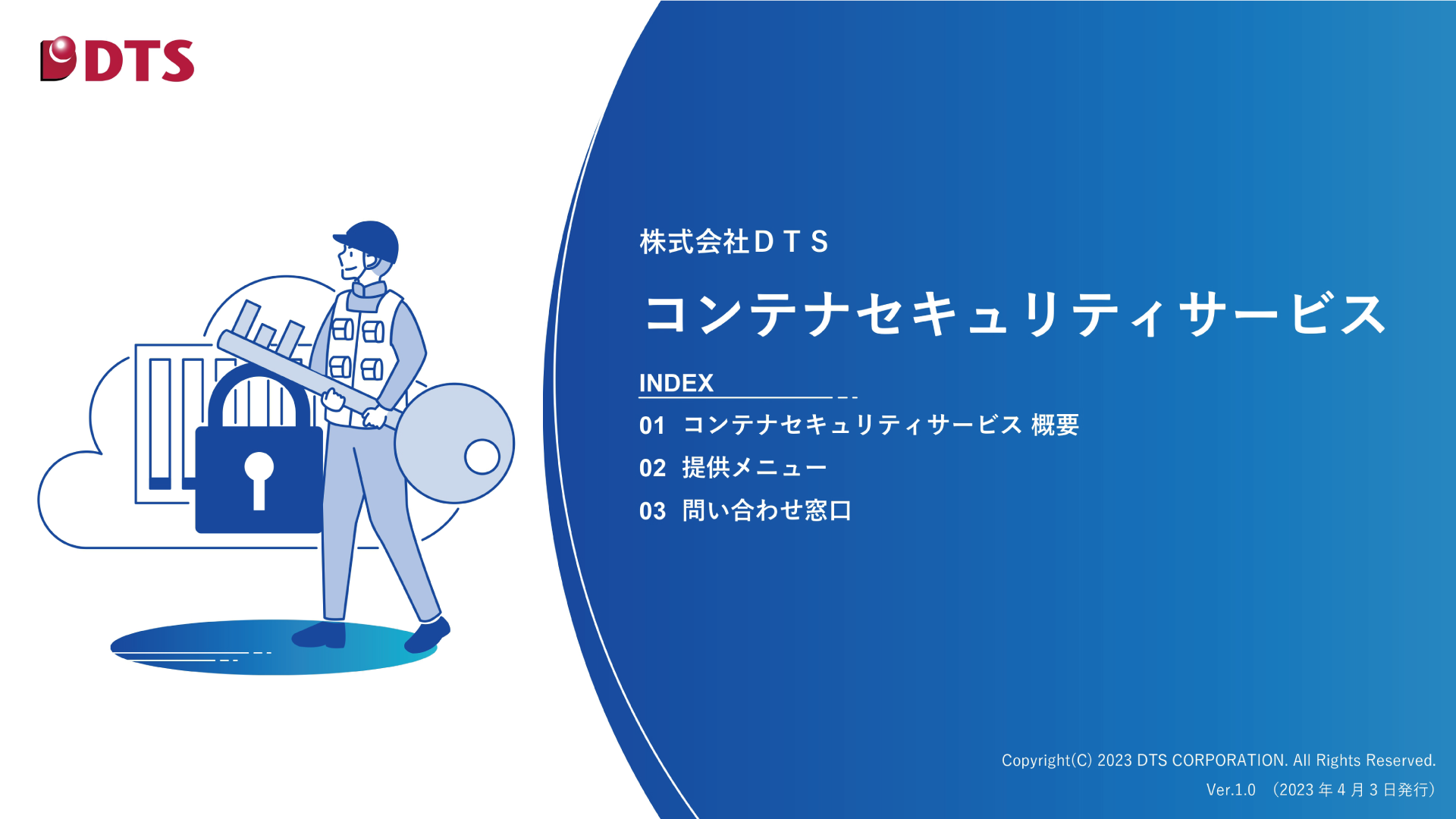 コンテナ利用によるセキュリティリスクに
コンテナ利用によるセキュリティリスクに
不安があるというお客様に!資料ダウンロード
-
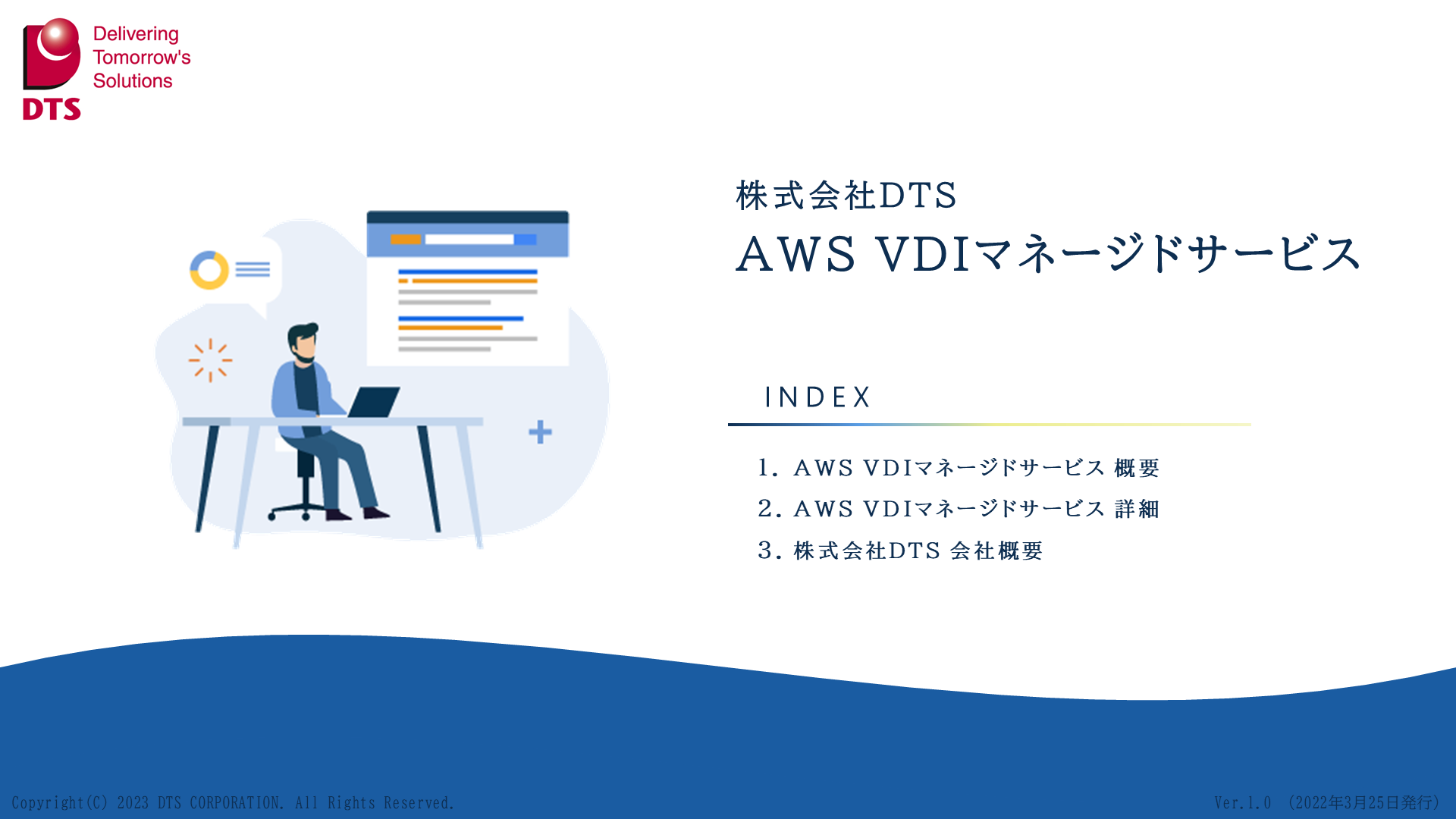 安心のテレワーク環境をすばやく整備!
安心のテレワーク環境をすばやく整備!資料ダウンロード
-
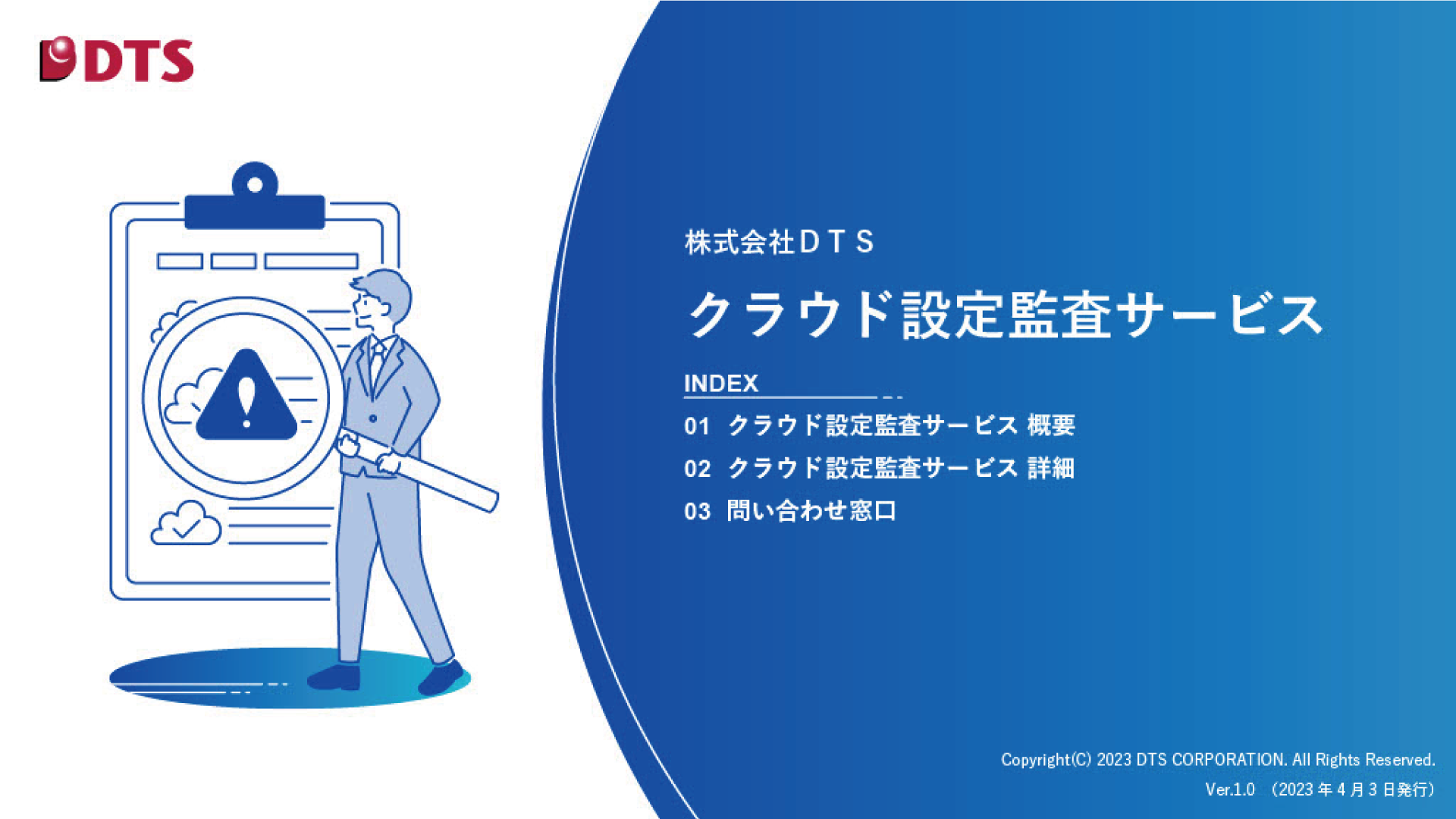 クラウドサービスの利用拡大によるセキュリティリスクの増加に
クラウドサービスの利用拡大によるセキュリティリスクの増加に
不安があるというお客様に!資料ダウンロード
-
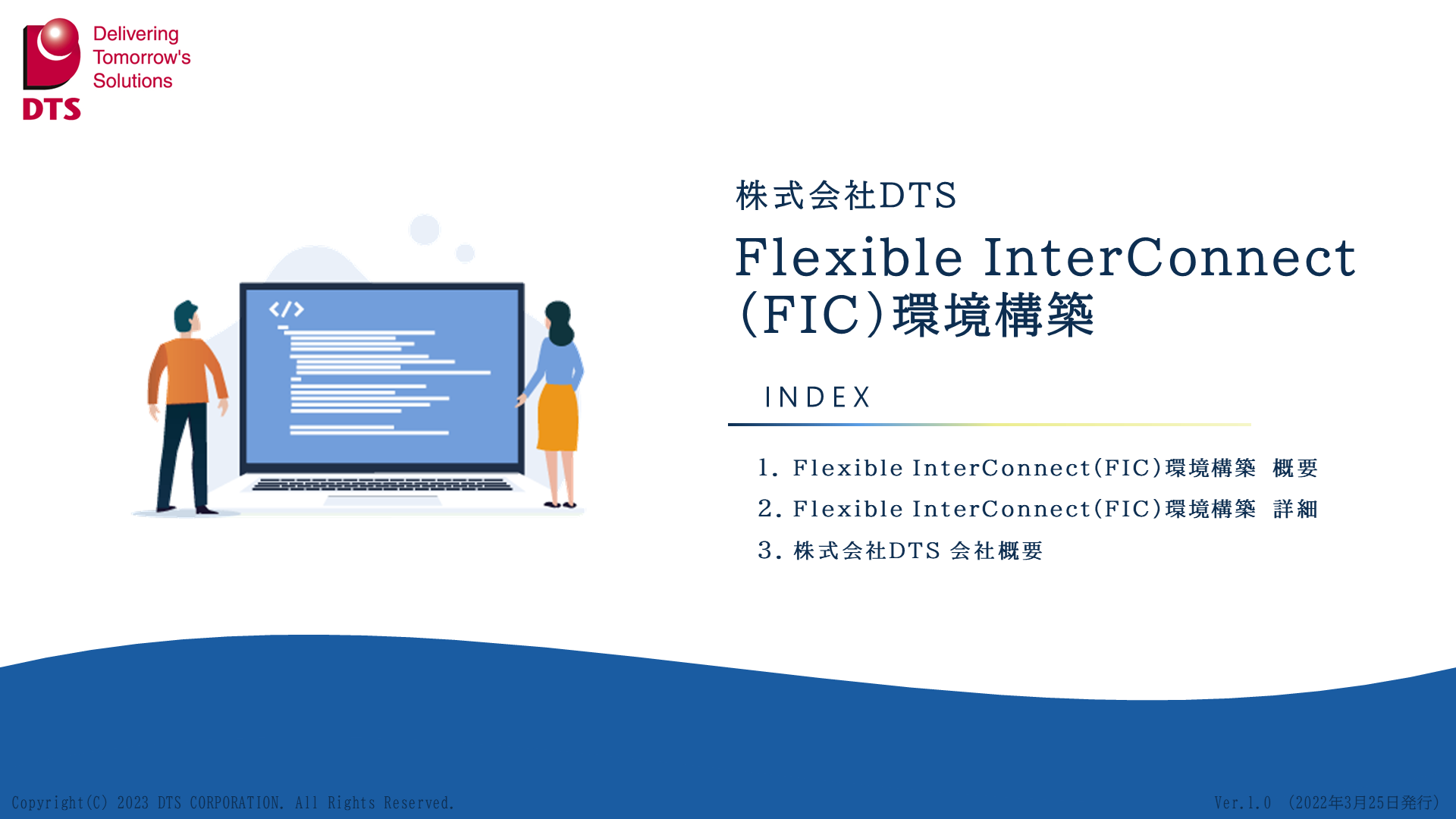 クラウドサービスにセキュアで接続したいお客様へ!
クラウドサービスにセキュアで接続したいお客様へ!資料ダウンロード